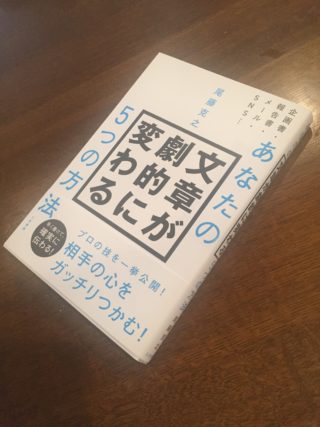
文章が劇的に変わる5つの方法
しばらく前に読んだ本です。 SNSで知り、AMAZONでいつの間にかぽちっとしていました。 3年ほど前からある程度の量の文章を書く機会を不定期で頂くようになり、文章の書き方についてはずっと自分なりに努力し考えてきました。
大阪の女性税理士 石田晶が、税金にまつわる情報をわかりやすくつづっていきます。
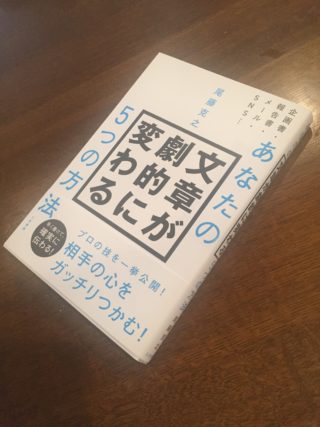
しばらく前に読んだ本です。 SNSで知り、AMAZONでいつの間にかぽちっとしていました。 3年ほど前からある程度の量の文章を書く機会を不定期で頂くようになり、文章の書き方についてはずっと自分なりに努力し考えてきました。

医療費は、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象とされています。 最近では医療費の支払い方も様々な方法がありますので、この場合はいつ支払ったことになるのか?というご質問もよくお受けします。

社会保険や生命保険などの給付金のうち一定のものは、医療費控除の対象である医療費からマイナスすることになっています。 この「保険などで補填される金額」として医療費総額から差し引くべきものとそうでないもの、についてのお話です。

家族を扶養にできるのかどうかで所得控除の額や税額が変わってきます。 その扶養の判断で重要な概念となるのが「合計所得金額」です。配偶者控除や扶養控除の要件に用いられます。

平成29年度税制改正により、配当所得等について所得税と住民税で異なる課税方式が選択可能であると明確化されました。ルールが変わったのではなく「統一化され明瞭になった」ということであり、納税者が自分に有利な方法を積極的に選択できるということです。
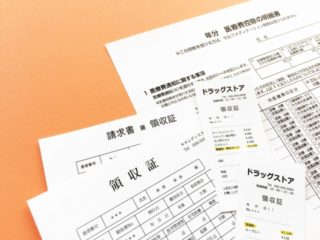
確定申告の医療費控除で、領収書の提出又は提示は不要となりました。領収書の代わりに「医療費控除の明細書」を提出します。「医療費通知(医療費のお知らせ)」もこれからは捨てないようにしましょう。

2017年から薬局で大きな変化が起きています。 「セルフメディケーション税制」がスタートしました。 医療費控除の特例、いわば市販薬に限定した医療費控除です。
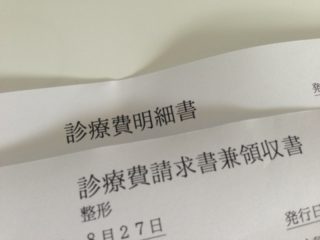
確定申告で最も適用する人が多い医療費控除。 まずは従来からある医療費控除について。 2017年から始まったセルフメディケーション税制については次回以降にお話しします。

サラリーマン(給与所得者)は殆どの場合、年末調整により所得税額が確定し納税も完了します。しかし他に所得がある場合等、サラリーマンでも確定申告が必要となる場合があります。

住宅ローン控除は今や、住宅購入時のポピュラーな制度となりました。 その「住宅ローン控除」は「マイホーム譲渡特例(3,000万円控除など)」とは併用できない、というお話です。